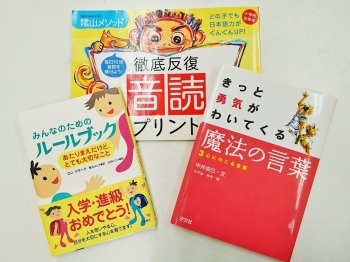先月、取材にいらした「まいぷれ江戸川区」さんが子育て支援企画で素敵な記事を書いてくれました。
https://edogawa.mypl.net/mp/kosodate/?sid=60174
『考える力』を育てる民間学童 ~ トゥモローキッズスクール
放課後の子どもたちが過ごす新しいスタイル!フルに頭を使っています
父母共にフルタイムで働く家庭での子どもが放課後を過ごす場所のひとつに、『民間学童』があります。学校に付属した公立の学童と比較して、保育時間が長いことや、独自のプログラムが充実していることなどが支持され、江戸川区内でも急増しているんです。
今回は、民間学童での子どもたちの過ごし方をレポート!ご紹介するのは、『トゥモローキッズスクール』(瑞江)です。実はこちら、江戸川区在住の1人のお父さんが、「小1の壁」を乗り越えるため、それまで勤めていた企業を退職して立ち上げた教室。特色のある教育方針にご注目ください。
「考える力」を育てるプログラム
トゥモローキッズスクール(以下TKS)で最も大切にしているのは、「自分で考える力」を育てること。普段の生活から自分で考える習慣をつけることが大切だと、代表の只友先生はおっしゃいます。
また、小学校1・2年の時期は学習の基礎をつくる大切な時期。この時期に勉強につまづくと、その先ずっと勉強嫌いになってしまうことが多いんだそう。そのため、TKSでは国語・算数の2教科に重点を置き、暗記ではなくきちんと理解できる指導を行っています。
トゥモローキッズスクールでの過ごし方
午後3時を過ぎると、学校を終えた子どもたちが集まり始めます。
ランドセルをしまうと、だれに言われるでもなく黙々と宿題を始める子どもたち。自らルールに則って行動する習慣が身についているんですね。
全員が揃うと、子どもの様子を見ながら先生が声をかけ、プログラムに誘います。
読む・聞く・書く・伝える…国語力を育てる
国語の学習で重要視しているのは、音読。文学作品の一節や詩歌、漢詩など、大人でも難しい文章をスラスラと読んでいきます。
まずは画面に映された文章を読むことから始め、何度も反復し、覚えるまで繰り返すんだそう。
友だちを前に堂々と発表する子どもたち。間違えずに暗唱できた子には「すごーい!!」、ちょっとだけ間違えてしまった子には「惜しいっ!」といった声が飛んでいました。
「低学年の段階で意味まで理解することは求めていません。でもこの音読が、将来文章を書く時のベースになっていきます。いわば種まきですね。」と只友さん。難しそうに見える暗唱も、友だちの発表を聞いているうちに自然と覚えていくんだとか。
またTKSでは、毎日必ず日記を書くのも特徴。「文章を書く」訓練はもちろんのこと、日記を書くことが、何にでも主体的に取り組むきっかけにもなるそうです。みんなの前で日記を発表したり、その内容に関した質疑応答をする時もあります。どうやったら自分の感じた思いが相手に伝わるか、より具体的な表現を模索することで、自分の意見を伝える力が育っていくのでしょう。
『こども新聞』を活用した学習にも取り組んでいます。低学年に対しては、先生が新聞を読み聞かせ、内容を説明します。
一方的に読むだけではなく、「この言葉わかる?」「どういう意味だと思う?」「何を言ってるかわかった?」など声掛けをし、子どもの発言を引き出しながら、理解を深めていました。
新聞を読む力のある子どもは、自力で記事を読み、言いたいことや自分の考えなどをまとめるワークに挑戦。学習を通して、読む力が高まっていることがうかがえます。
間違うことを恐れない
この日の読み聞かせの教材として、『我以外皆我師(われ以外みなわが師)』という言葉が取り上げられていました。
小学校低学年にはかなり難しい言葉…でも先生は説明より前に「どういう意味だと思う?」と問いかけます。
するとスッと手を挙げた子が。「わかるよ。お菓子だよね!」……しばらくして「わが師=和菓子」の勘違いとわかってみんな爆笑!
ほほえましい一件でしたが、ここにTKSでの学習の根っこがあるような気がしました。
というのも、全てのプログラムを通して先生が何度も口にしていたのは
「間違っていいんだよ」
「大きな声で、自信を持って!」
「失敗しないとできるようにならないよ」
という言葉。
たとえ間違えていたとしても、自分の頭で考えた意見をみんなの前で発表できたことは素晴らしいことだし、笑われたとしてもその間違いは印象深く記憶に残ったことでしょう。
和菓子を食べるたびに、『我以外皆我師』の言葉を思い出すかもしれませんね。
「暗記」ではなく「理解」することで応用力が育つ…算数
算数は、学校の進度に合わせた基礎の内容をしっかり押さえながら、先取り学習もしています。
先生自作のパワーポイントを使って、計算問題の練習。誰が一番早く答えられるか競う子どもたちはなんだか楽しそう。意欲や集中力が倍増しているようでした。
計算問題を反復していると、子どもたちは数字の組合せと答えを暗記してしまうことが多いんだそう。次のステップに進んだ時に応用するためには、『考え方』をしっかり理解していることが必要。そのために工夫が凝らされたプログラムになっていました。
「ついて来れていないなと感じる子どもがいればすかさずフォローしています」と只友先生。ホワイトボードや積み木などを使って、マンツーマンでわかりやすく教えているそうです。
勉強したあとはしっかり遊ぶ!遊びの時間も脳はフル稼働です
たくさん頭を使った後は、おやつを食べてひと休み。あとは、お父さん・お母さんが迎えに来るまで、公園で体を動かしたり、部屋でボードゲームをしたりして、友だちとたくさん遊びます。
…というわけで、盛りだくさんなレポートとなりました。
今回おじゃまさせていただいたのは、通常のプログラム。別の曜日には、ネイティブ講師による英語のプログラムも実施しています(週2回)。夏休みには、科学未来館や動物園、海に出かけたりと、教室を飛び出したプログラムを楽しんだそうです。
編集後記
トゥモローキッズスクールは1学年6名の少人数制をとっているため、子どもひとりひとりに目が届きやすいのがポイント。使用する教材も理解度に合わせて毎週作り直すなど、きめ細かい教育を行っているそうです。
「学習の時も遊びの時も、とにかく子どもを観察しています。大事なことは結果ではなく、些細な過程を褒めてあげること。そのためにも観察が必要なんです。」
と語る只友先生からは、子どもたちに対する愛情が感じられました。それは、先生自身が同じ年頃の子どもを持つ父親であることも大きく影響しているでしょう。
民間学童に関しては、「公立の学童保育では保育時間が短すぎる人のための受け皿」というイメージが強かった私。しかし、今回トゥモローキッズスクールにおじゃまして、そのプログラムの充実ぶりに驚かされました。
長い『放課後』という時間を有意義に過ごせる点において人気が高いのもうなずけます。もちろん費用はかかりますが、平日子どもを習い事に連れていくのが難しい共働き世帯にとって、民間学童で様々な教育を受けられることはありがたいことです。
江戸川区内にはほかにも多くの民間学童があり、サービス内容やプログラムに特色があります。よく吟味して、子どもが心地よく過ごせるところが選べるといいですね。

「小1の壁」を感じず、安心して働けるように。また、国際化・多様化する社会で子どもたちが活躍できるように。そんな思いからスタートした、アットホームな民間学童です。
音読や、毎日の日記、英会話、算数といった学習を通して、「自分の意見を伝える力」「計算力」「作文力」を育みます。詳細はこちらから↓
公式ウェブサイト
Facebookページ
- 投稿タグ
- メディア